著者・出版社情報
著者:クリス・ミラー
出版社:ダイヤモンド社
概要
本書『半導体戦争 世界最重要テクノロジーをめぐる国家間の攻防』は、現代社会の中でいかに半導体が「国家の命運」や「国際政治のパワーバランス」を左右するのかを、歴史と地政学的視点から解きほぐしていく作品です。著者のクリス・ミラーは、経済史と国際関係を専門とする研究者として、半導体が21世紀最大の戦略資源になると断言し、過去と現在の事例を多角的に検証しています。
かつての世界は「石油」を争って国家同士が激しい駆け引きを繰り広げてきましたが、いまやデジタル社会の根幹を支える半導体がその役割を担いつつあります。スマートフォンやパソコンはもちろん、AI、5G通信、電気自動車、自動運転、軍事兵器の制御といったあらゆる先端領域が高性能半導体の供給に依存しています。つまり、半導体が不足すれば経済活動はストップし、軍事面でも後れを取る。だからこそ、アメリカや中国を筆頭に各国は優位性を確保すべく苛烈な競争を繰り広げているのです。
本書は、ソ連崩壊後から現在に至るまでの世界各国の政策や企業動向、ファウンドリ企業の台頭、製造装置メーカーの独占技術など、詳細なデータと事例を紐解きながら、「半導体=石油に代わる次の地政学的資源」と位置づける壮大な物語を描いています。
活用法
国際政治と経済を総合的に理解するための“必読”文献として学ぶ
本書は、単なる技術解説書ではなく、半導体を軸に国際政治や経済がどのように絡み合っているかを克明に示す一冊です。次のような観点で学ぶと、理解が深まります。
- 冷戦構造から現在までの地政学的移り変わり
ソ連が崩壊するまで、アメリカとソ連の間で軍事用ICの開発競争が激化し、それが民生用の発展にも繋がった歴史的経緯が描かれています。冷戦後は中国や台湾、韓国が台頭し、それぞれが半導体を“国の命運をかけた産業”として育成してきた。 - 米中の経済覇権争いと輸出規制
AIやスーパーコンピュータの性能は、先端プロセスを使った最先端チップに左右されるため、アメリカはオランダのASMLなどと協力して中国への先端装置輸出を制限。一方で中国は独自の製造技術を確立しようと莫大な投資を行う。この綱引きが世界の半導体市場を大きく揺るがしている。 - サプライチェーンと安全保障
台湾のTSMCや韓国のサムスンの存在が、台湾海峡や朝鮮半島の地政学リスクと直結している事例は極めて示唆的。ファウンドリ企業1社が世界の先端ロジックチップをほぼ独占しているため、もし台湾が紛争に巻き込まれれば、全世界のハイテク産業が大打撃を受ける。
こうした国際情勢を俯瞰的に把握できるため、政治学や経済学の学生、国際ビジネスに興味を持つ社会人にとって“教科書”として使える内容です。関連する資料やニュースと併読すれば、さらに理解が進むでしょう。
エンジニアや技術者が自分の専門領域を広げ、“技術×地政学”の視点を得る
半導体企業やIT企業に勤めるエンジニア、またはそれらを志す学生にとっては、「半導体は技術力だけでなく政治や経済の動きにも大きく左右される」という視点が極めて重要になりつつあります。本書を読むことで、単にナノメートルの微細化やEUVL装置といった技術的トピックに留まらず、以下のような観点を学べます:
- サプライチェーンのリスク管理
海外の特定地域(台湾・韓国など)に生産拠点が集中している現実をどのように補完するか。国家や企業が多額の投資で国内にファブ建設を促す動きはなぜ必要か。 - 産業政策の理解
アメリカのCHIPS法、日本やEUの補助金など、国が莫大な予算を投じて“半導体自立”を目指す背景。こうした政策支援が技術ロードマップにどんな影響を及ぼすか。 - 競合他社や各国の戦略
ファウンドリ型(TSMC、サムスン)、IDM型(インテル)、装置メーカー(ASML、東京エレクトロン)などのビジネスモデルを俯瞰し、それぞれの強みや歴史を認識する。
技術者がこれらを理解しておくと、研究開発や製品企画のステージで大きな視野を持て、長期的にキャリアアップや事業リーダーとして活躍する可能性が高まるでしょう。
投資家やビジネスパーソンが半導体セクターの動向を読むための“マクロ視点”を得る
株式投資家やアナリスト、コンサルタントにとって、半導体セクターの動向は非常に重要ですが、テクノロジー面だけでなく地政学が大きく絡むため、表面的な企業決算や技術力ランキングだけでは判断が難しい領域です。本書を手掛かりに、以下のような切り口で分析できます:
- 先端プロセス投資の帰趨
例えばTSMCがどの国に新工場を建設するか、サムスンがどのノードで優位を取るか、インテルの再興戦略は実現可能か、といったトピックを把握しておく。 - 各国の規制や輸出制限
米国が中国への半導体製造装置輸出を規制すれば、中国市場で大きく成長していたASMLやラムリサーチ、東京エレクトロンなどの業績に影響が及ぶ。また逆に中国が独自技術を確立すれば、それも世界シェアに変動をもたらす。 - 経済サイクルとの関連
半導体は景気に左右されやすいが、AIブームや自動車の電動化など構造的な需要増もある。マクロ経済の先行きだけでなく、今後数年のテクノロジー動向を総合評価する必要がある。
本書に掲載される具体的な国家の施策や企業の戦略は、投資判断を行う際の重要な背景知識となります。短期的な景気変動だけでなく長期的な技術ロードマップと地政学リスクを踏まえることで、より精度の高いビジネス分析が可能になるでしょう。
企業経営者・戦略担当がサプライチェーンやイノベーションのリスクマネジメントに活かす
現代のあらゆる業種は、何らかの形で半導体に依存しています。自動車メーカー、家電・ロボット開発、さらには金融やネットサービス業までも、ハードウェアを伴うサービスであれば半導体の安定供給は死活問題。
本書を活用し、以下のようなリスクマネジメントや経営戦略に取り組むことが考えられます:
- 代替サプライヤー確保
もし主要サプライヤー(TSMCなど)が紛争や災害で生産停止したらどうなるか。自社の製品計画が滞らないよう複数の調達先を確保する必要がある。 - 在庫ポリシーと需給調整
半導体は調達リードタイムが長い上に、需要変動が激しい。過剰在庫リスクや欠品リスクをどうマネージするか、中長期での在庫戦略を再考する。 - 国際情勢に基づく製品戦略
米中対立が深刻化すれば、中国向け製品への規制が強まる。必要ならば設計を変更して輸出規制を回避するか、あるいは生産拠点を移転するかなど、先手を打ったビジネス設計が重要。 - 次世代技術投資
量子コンピュータやAIに不可欠な先端チップにアクセスできるかどうかが、イノベーションの成否を左右する。パートナー企業選びや研究開発拠点の立地なども含め、本書が語る世界のパワーバランスを踏まえて検討する。
経営者や戦略担当がこれらの視点を取り入れるだけで、半導体をめぐる国家間の攻防が自社のビジネスにどう影響するかをよりリアルに理解でき、柔軟な対策を立てられるでしょう。
一般読者が“テクノロジーと世界”を繋ぐ線を知り、将来を見通す材料とする
本書は専門家向けだけでなく、「今の世界がどう動いているのか」を幅広く知りたい一般読者にも最適です。半導体の技術的な背景はそこまで詳しくなくても理解できるように解説されており、読後にはこんな視点が得られるはずです:
- なぜスマホやPCが進化するのに“半導体が要”なのか?
5GやAIのような技術はどれも高性能チップを必要としており、その製造現場がどこに集中しているかを知ると、国際ニュースの意味が深く分かる。 - 地政学リスクと身近な生活
台湾有事や米中貿易戦争がニュースで報じられるが、それが自分の生活やモノの価格に直結する理由を本書から学べる。 - 歴史の繰り返し
かつて石油が資源争奪の主役だったように、いまは半導体がその地位を占めている。自然資源と違い「人の技術」に依存する分、より複雑なパワーゲームになっている点も興味深い。
このように、本書は世界の動向と自分の日常を結びつける大きな橋渡しとなるでしょう。大学生や高校生が国際社会に関心を抱くきっかけとしても優れた教材だと考えられます。
所感
半導体は「人類が作り出した最も複雑な製品」とも言われ、その開発・製造には高度な技術と莫大な資金が投じられてきました。かつて国際政治の焦点は石油をめぐる駆け引きに集まっていましたが、本書を読むと、その焦点がいま半導体にシフトしているのは明白です。
印象的なのは、半導体産業が単なる技術や経済の問題で終わらず、実際に軍事バランスやAI覇権競争にも直結しているという点です。自動車のECUやミサイル誘導システムからデータセンターのGPUまで、どこを取っても高性能チップが不可欠。供給が止まれば、デジタル社会がストップする――そんな世界を想像すると、地政学的リスクがいかに現実の脅威になるかが肌で感じられます。
著者のクリス・ミラーは、歴史的背景と国際関係の分析をベースに「このまま米中対立が進むと、さらにサプライチェーンが再編され、半導体市場は分断されるかもしれない」と警鐘を鳴らしています。TSMCやサムスンが主導するファウンドリの集中構造、日本や欧州、アメリカが先端製造装置や素材を握る状況で、中国がどこまで自給自足体制を構築できるのかは今後の焦点でしょう。
私は本書を通じて、冷戦下でのソ連と米国のIC開発競争がいかに新たな経済秩序を作り上げ、現在のシリコンバレーやアジアのハイテク集積へ繋がったのかが非常に興味深く感じました。技術開発や企業戦略の変化が、国家の思惑や外交政策とこれほどまでに絡み合う構図は、まさに「21世紀の資源戦争」と呼ぶにふさわしい。読後感としては、「テクノロジーは政治や軍事から切り離せないのだ」という現実を再認識させられます。
まとめ
『半導体戦争 世界最重要テクノロジーをめぐる国家間の攻防』は、石油に代わる新たな資源と言われる半導体をめぐって、どのように各国が競争し、どんな政治・軍事・経済的なリスクが生じているかを克明に描いた一冊です。
- 歴史的視点:ソ連との冷戦期から、パーソナルコンピュータ誕生、アジアの半導体企業の台頭、そしてAI時代まで、半導体がいかに国力や安全保障を左右してきたかを体系的に学べる
- 地政学の視点:台湾や韓国など、先端プロセス製造拠点が特定地域に集中する現状は、国際社会の不安定要素であり、それが台湾海峡や朝鮮半島の政治リスクと結びつく
- 技術と市場支配:EUV露光装置を独占するオランダASML、GPUでAI領域を独走するNVIDIAなど、特定企業が極めて重要な地位を握る“寡占的”構造が明確化
- 米中対立:AI・5Gでリードしたい中国は先端チップ技術を国策として推進するが、アメリカが強力な輸出規制で牽制。これにより各国や企業が巻き込まれ、世界規模でバリューチェーンが分断されるリスクが高まる
「半導体が世界を制する」というフレーズは大袈裟に聞こえるかもしれませんが、スマホや車の生産が半導体不足で止まる現象を経験した今、もはや疑いの余地はありません。本書は、そんな半導体をめぐる巨大な権力闘争と複雑なサプライチェーンの全貌を明らかにし、私たちに「テクノロジーと政治は切り離せない」という洞察を与えてくれます。
国家戦略や企業の未来を理解したい人だけでなく、日常生活に根付くハイテク製品がどのように世界地図を塗り替えようとしているかを知りたい一般読者にもおすすめです。半導体という“見えない資源”が現代社会の動脈であることを、痛感させられる一冊と言えるでしょう。

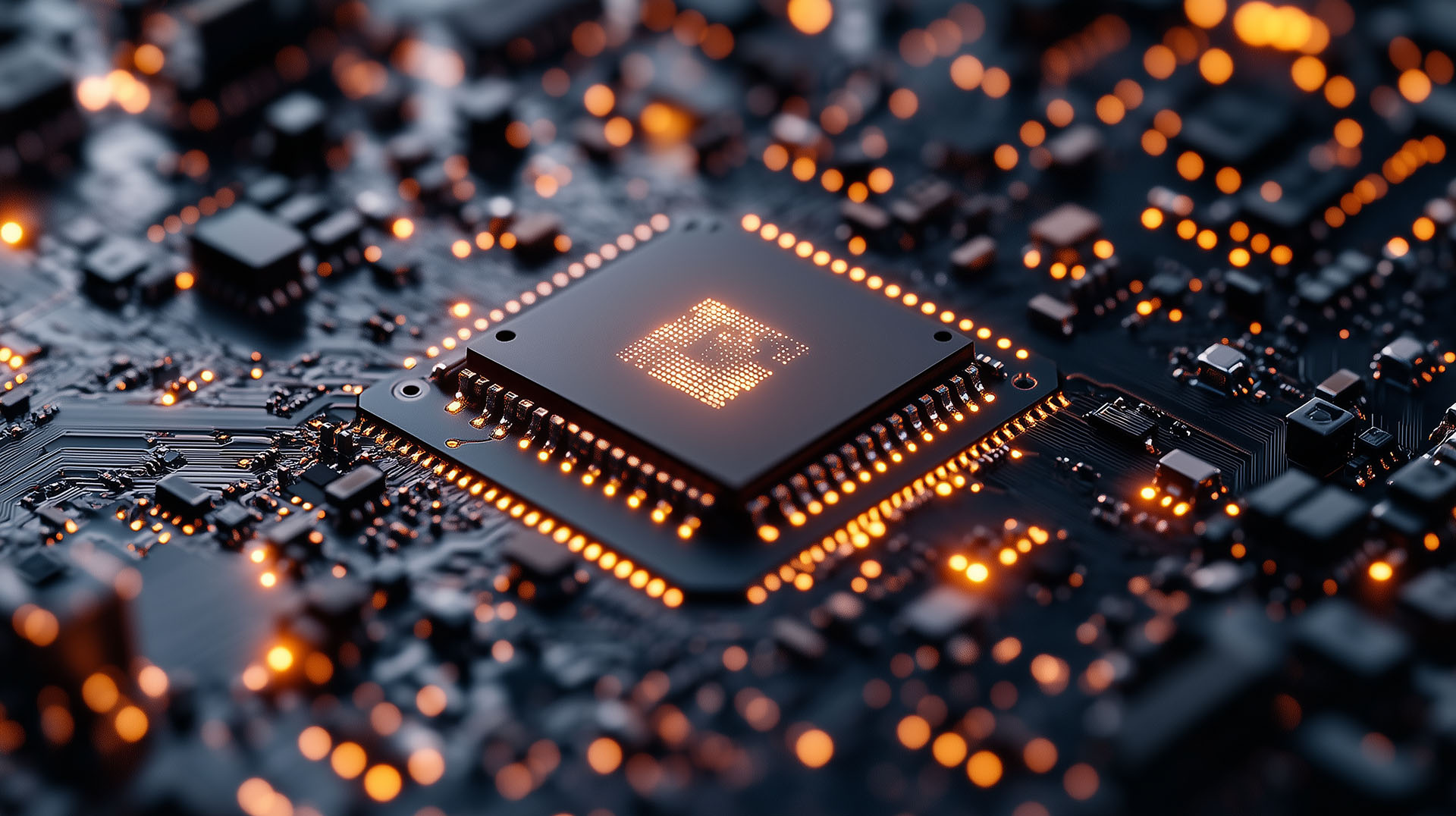


コメント