著者・出版社情報
著者:フランク・ラポルト=アダムスキー
出版社:東洋経済新報社
概要
『腸がすべて: 世界中で話題!アダムスキー式「最高の腸活」メソッド』は、イタリアを拠点に活動するセラピストフランク・ラポルト=アダムスキー氏が提唱する腸活(腸内環境を整えるための生活習慣や食事法)に関する一冊です。現在、世界中でさまざまな食事法や腸活メソッドが注目を集めていますが、本書ではアダムスキー式として“食品を消化速度によって分け、正しい時間と組み合わせで食べる”という独自の考え方を提示。腸の動きや消化のメカニズムを意識することで、身体全体の健康や、便秘・肌荒れ・不眠などの不調解消に役立てようというものです。
著者は、長年にわたり人々の生活習慣や食事スタイルを分析し、実際のクライアントへの施術を通じて独自の理論を確立しました。その核心は、「腸にとって相性の悪い食材を同時に摂らない」ことで腸内をスムーズに動かすというシンプルなもの。とはいえ、食材が「ファスト(消化が早い)」「スロー(消化が遅い)」「ニュートラル」に分類され、どの時間帯にどれと組み合わせて食べるかなど、具体的なルールが詳しく説明されているため、すぐに実践できるヒントが満載です。
一方で、多くの食事法と同様、本書に書かれていることが万人に完全に合うわけではありませんし、あくまで「ひとつの選択肢」として理解するのがよいでしょう。腸の働きは個人差が大きく、生活リズムや遺伝的背景によっても効果は変わる可能性があります。それでも、腸活に興味がある人や、何らかの不調を感じて食事を見直したい人にとって、この「アダムスキー式」は新たな視点を提供してくれるでしょう。
活用法
腸内環境を本気で整えたい人のデイリールーティンとして
特に、本書は「便秘」「肌トラブル」「疲れやすい」など、腸の不調と関連していそうな悩みを持つ人におすすめです。最初に著者が説く「食品の3分類(ファスト・スロー・ニュートラル)」を頭に入れ、それに基づいて買い物や調理、食べる順序を少しずつ変えてみるとよいでしょう。
1. 食材の分類を意識する
– ファスト(消化が速い)食品:果物やヨーグルト、トマトなど
– スロー(消化が遅い)食品:肉・魚・野菜・穀物など多くの一般食品
– ニュートラル:オリーブオイル、バター、コーヒーなど
最初は「これはファストか?スローか?」と混乱しやすいので、メモや本書のリストを参照にしながら習慣化するとよいでしょう。
2. 食べ合わせのルールを導入
アダムスキー式では、ファストとスローを同時に食べるのを避けるのが基本。たとえば、肉(スロー)とフルーツ(ファスト)を一緒に食べないなど。外食が多い人は難しいかもしれませんが、3食のうち1~2食分だけでも徹底すれば効果を感じる可能性があります。
3. こまめに腸を休ませる時間を作る
「食と食の間に4~5時間開ける」「就寝3時間前に食事を済ませる」など、腸に余計な負担をかけずに動きを整えるコツも紹介されています。忙しい人ほどこのポイントは見落としがちなので、スケジュール管理と合わせて実践するとよいかもしれません。
他の食事法と比較しながら“自分に合った腸活”をカスタマイズする
腸活といえば、「発酵食品を摂る」「食物繊維を増やす」「ファスティング」など多彩なアプローチが提案されてきました。アダムスキー式もその一つであり、完全に置き換えなくても、部分的に取り入れることが可能です。たとえば、普段は別の方法を実践しているが、食べ合わせだけはアダムスキー式を意識する、といったやり方です。
1. メインの食生活に“組み合わせルール”を加える
もし低糖質ダイエットやプラントベースなど他の食事法を実践中であれば、そこに「ファスト食品とスロー食品を分けて食べる」だけ追加してみるとよいでしょう。すると腸の負担が減り、より快適な消化を実感するかもしれません。
2. 人工添加物や加工食品にも目を向ける
本書は主に自然食品の中での“消化速度”を議論しているため、加工食品やジャンクフードは前提としてお勧めされていません。たとえば、いくらファスト食品に分類されるフルーツでも、加工された糖分入りフルーツソースは事情が変わるなど、応用力が求められます。結果的に、食全体を健康的に見直す流れにも繋げられるでしょう。
腸活を指導する医療関係者・サロンオーナーの知識拡充に
このメソッドは、日本ではまだ十分に広まっていない新しい形の腸活理論なので、栄養士や医療従事者、エステティシャンなど「健康や美容をサポートする」専門家にとっては、患者や顧客へアドバイスする際の新しい引き出しとして有用です。
1. カウンセリングでの選択肢として
患者やクライアントによっては、糖質制限やカロリー制限が続かない、あるいは発酵食品で体質が合わなかったりするケースもあるでしょう。アダムスキー式の“組み合わせ制限”は比較的柔軟に応用でき、他のメソッドと衝突しにくい面があるため、一つの選択肢として提案するとよいかもしれません。
2. 維持が難しい人へのアドバイス
実際は、食べ合わせルールを厳守するのが難しく、外食や仕事の関係で破ってしまう人も多いでしょう。その際、「週末だけは徹底する」「夕食だけはファストとスローを分ける」など部分導入でメリットを感じる方法を教えると、クライアントの長期継続率が上がる可能性があります。
日々の健康管理とセルフケアとして取り入れ、効果を検証する
「腸活」はブームと言っても過言ではない現代ですが、本書を読んだからといって即座に全てを信用する必要はありません。むしろ“自分の身体で試してみる”という姿勢が大切です。2~3週間ぐらい徹底して食材の区分と食べ合わせを守ってみて、便通の変化や体調・気分の変化を記録してみる。それで調子が上向けばあなたに合った方法と言えますし、イマイチであれば他の方法を探す、という程度の柔軟性が望ましいでしょう。
1. 食事日記をつける
具体的には、「何時に何を食べたか、ファストかスローか」「体調はどうだったか」を簡単にメモすると変化が把握しやすくなります。著者によれば、わずか数日で腸の動きが改善したという声もあるそうなので、改善すればモチベーションもアップ。
2. 水分や睡眠など他の要因にも注意
腸に影響するのは食事だけではありません。水分摂取、睡眠、ストレスなど多くの要素が絡むので、アダムスキー式のみを実践しても十分な水分を摂らなければ効果は半減しますし、過度なストレスで胃腸が不調になれば分からなくなってしまいます。全般的に生活習慣をバランスよく整える視点が大切です。
自分の体質や各種検査の結果と照らし合わせる
最後に、本メソッドを“鵜呑み”にするのではなく、医師や専門家と相談しながら進めることを推奨します。特に慢性疾患や食物アレルギーがある人、薬を常用している人などは相性を確認しないと逆効果になる恐れも。最近は「腸内フローラ検査」など手頃な価格で受けられる検査もあるので、実践前後で比較してみると客観的な評価ができます。
1. 医師や管理栄養士の視点
特定の食品を制限するダイエットは栄養バランスに偏りが出がちです。アダムスキー式でも果物を大量に食べる場合があったり、肉や魚を別のタイミングで食べるなど複雑なローテーションを組むことになるため、栄養素の摂取状況を確認する意味でも専門家に相談するメリットは大きいです。
2. 腸内環境改善の効果測定
実際に腸内細菌の種類やバランスがどう変化したかを検査すれば、主観的な「お腹の調子が良くなった」以外のデータを得られます。もし数値上の改善が見られれば、モチベーションがさらに上がるでしょうし、逆に変化がなければ次のステップや別のアプローチを検討できます。
所感
本書の最大の特色は、なんといっても「食品を消化の速さで分類し、それを同時に食べない」という明快なルールでしょう。消化器官に負担をかけないという考え方は確かに一理あり、過去にも「フードコンバイニング」など類似の概念が一部で広まったことがあります。ただ本書は、それをさらに「ファスト」「スロー」「ニュートラル」という3カテゴリに分割し、明確な一覧を提示してくれるため、理解しやすく実践に移しやすい点が良いと感じました。
とはいえ、著者の主張が万人に当てはまるわけではない点も強調したいです。腸の状態は人それぞれで、例えば果物や乳製品の摂取で下痢や腹痛が起こる人もいますし、肉(スロー)をあまり食べられない人もいるでしょう。さらに日本人の食文化は米を中心とした和食が多く、本書で推奨される地中海式の食材とは若干異なる点もあります。したがって、実践する際は自分の体調や食習慣を踏まえ、柔軟にアレンジする姿勢が必要だと思われます。
「腸活はやってみたいけど、ヨーグルトや納豆を大量摂取する一般的な方法が合わない」「いろいろ試してもイマイチだった」という人は、本書のような視点から食べ合わせに着目してみると新しい発見があるかもしれません。数多くの事例や実践者の声が紹介されていて読みやすく、ちょっとした日常の変化(ファスト・スローを分ける)で意外と大きな効果が得られる可能性を示唆しているので、試してみる価値はあると感じます。
まとめ
『腸がすべて: 世界中で話題!アダムスキー式「最高の腸活」メソッド』は、イタリア発のセラピストフランク・ラポルト=アダムスキー氏による独自の腸活理論です。食材を「ファスト(消化が速い)」「スロー(遅い)」「ニュートラル」に分類し、同時に食べる組み合わせを制限することで、腸の動きを最適化し、便秘や肌トラブル、不眠など様々な不調を解消しようというメソッドが中心となっています。以下のポイントが大きな特徴です:
- シンプルな3分類: 果物やヨーグルトなどは“ファスト”、肉魚や穀物は“スロー”、オイルやコーヒーなどは“ニュートラル”と区分し、同じ食事でファスト&スローを混ぜない。
- 「腸にやさしい時間の空け方」: 食と食の間をある程度あけて腸を休ませたり、寝る前の食事を控えたりすることで、腸に負担をかけにくくする。
- 日本人への応用: 主に地中海的な食文化を前提としているが、日本の食材にも置き換えが可能。とはいえ、米や魚介類などの扱いは工夫が必要で柔軟に対応。
- 注意点: すべての人に合うかは個人差が大きい。既存の病気やアレルギーを持っている場合は医師と相談を。あくまで他の腸活法と比較しつつ試すのがベター。
今や「腸活」は多種多様な方法論が溢れており、どれを選べばいいか迷う方も多いでしょう。本書は、その中でも「食べ合わせ」に注目した点が特徴で、比較的実践しやすいルールが多いこともあり、腸活初心者でも導入しやすいメリットがあります。また、人によっては「夜のご飯だけはファストとスローを分ける」といった部分的な採用でも効果を感じるかもしれません。大切なのは自分の身体と対話しながら実践し、少しずつ生活に取り入れていくこと。さらに、医師や栄養士と協力して評価することで、より確実な効果検証ができるはずです。
腸の健康は身体全体の健康と直結しており、免疫力やメンタル面にも大きな影響を与えると考えられています。もし今まで何かの腸活を試して効果を実感できなかった方は、「アダムスキー式」を一度読んでみて、自分に合いそうな部分をトライしてみるのも一つの手。シンプルなルールながらも新鮮な発想や豊富な事例が載っているので、新しい気づきを得られるかもしれません。腸が快適になれば、毎日の生活がもっと軽やかになる可能性がある――その入り口として、本書は十分なヒントを提供してくれるでしょう。

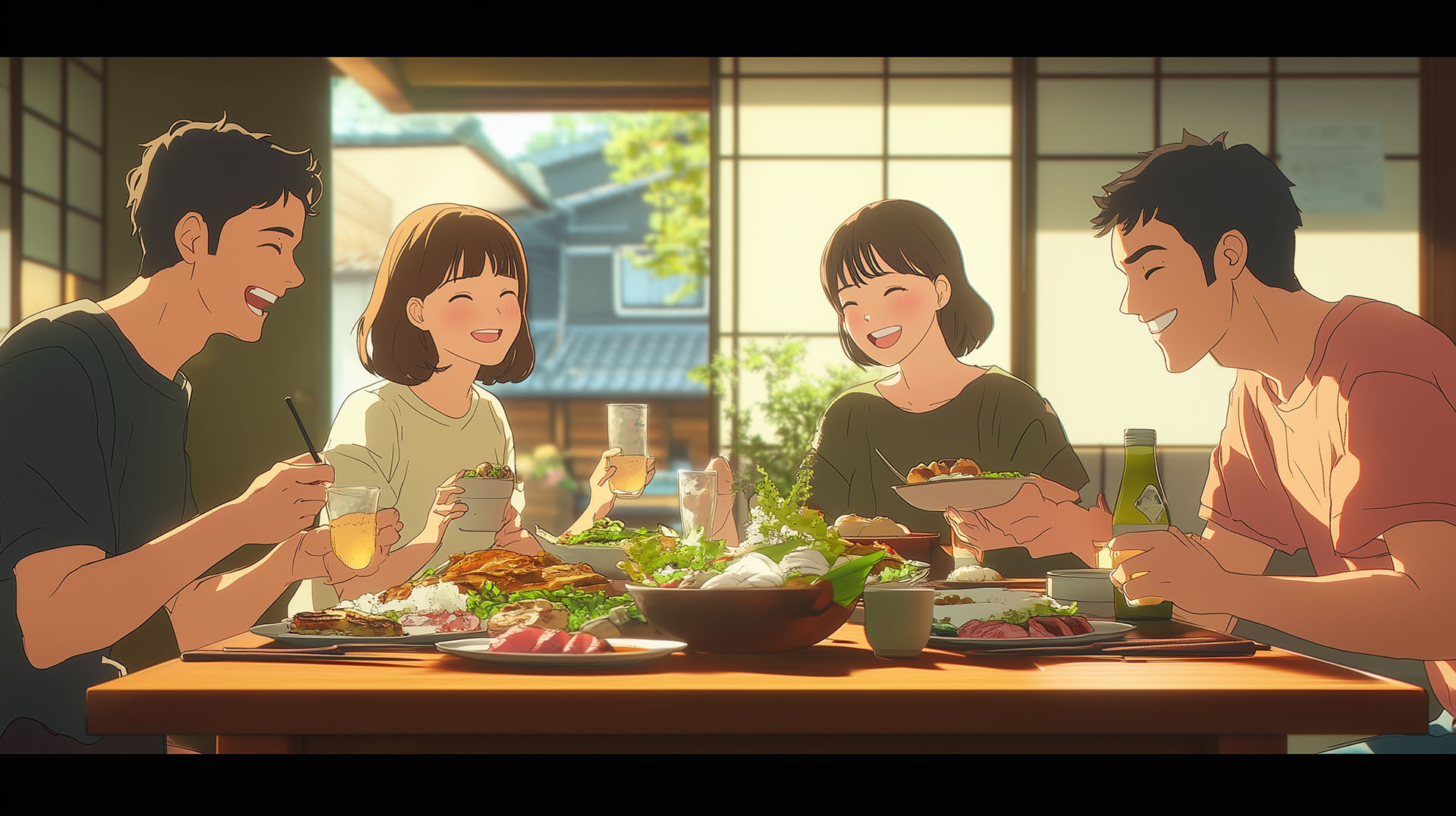


コメント