著者・出版社情報
著者:メアリー・V・ソラント
出版社:星和書店
概要
私たちは、ADHDという言葉を耳にする機会が増えてきましたが、それが大人になってからも継続しうることは、近年ようやく多くの人に認知されてきました。子どもの頃だけの障害ではなく、大人になってからも不注意や衝動性、あるいは落ち着かなさといった症状に悩んでいる人は意外とたくさんいます。そして、大人になると仕事や家事、人間関係などで要求される「実行機能」が増えてくるため、ADHDを抱えていると生活全般が混乱しやすいのも事実です。
著者のメアリー・V・ソラントは、そうした大人のADHDに伴う実行機能障害をどう治療していくかを専門としており、本書『成人ADHDの認知行動療法 実行機能障害の治療のために』を通じて、非常に実践的なノウハウを提供しています。ADHDといえば薬物療法(刺激薬など)が主な治療法として広く知られていますが、ソラント氏はそこに加えて認知行動療法(CBT)を活用することで、本人の生活の質をさらに高めるアプローチを確立。時間管理や優先順位づけなどの行動面への具体的アプローチはもちろん、「自分はダメだ」と否定的に捉えてしまう思考パターンを修正していくための方法を示し、大人のADHDに希望を与えてくれる内容となっています。
本書は、専門家や支援者に向けた治療手引きとしての面が強いですが、ADHD本人やその家族が読んでも十分に理解できるよう丁寧に解説されているのが特徴です。実行機能障害とは何なのか、どういった形で困りごとが起きやすいのか、そしてどのようにCBTを適用していくと改善や自己管理が図れるのか――これらが体系的にまとめられています。従来は「薬を飲むしかない」と思われがちだった成人ADHDですが、ソラント氏のプログラムを通じて、より柔軟かつ実践的に「困難を対処する術」が見えてくるでしょう。
活用法
自分の実行機能の弱点を客観的に把握する
成人ADHDと一口に言っても、人によって症状の現れ方は千差万別です。多くの人が苦手とするのは、時間管理や優先順位づけ、計画といった実行機能関連の課題。例えば「後でやろうとして先延ばししてしまい、締め切りに間に合わない」「やることを忘れがちで、常にバタバタしている」といった困りごとが思い当たる方も多いかもしれません。
本書の基本スタンスは、まず「自分の実行機能のどこが苦手か」をきちんと客観視することです。つまり、漠然と「自分はダメだ」と思い込むのではなく、「時間を見積もるのが苦手」「複数のタスクを並行処理するのがつらい」など、具体的に細分化していきます。その上で、「どうすればそこを補えるか」「どんな工夫があれば遅刻や締め切り遅れを回避できるか」を考えるわけです。
特にADHDだと、自分でも何に困っているかよく分からないまま、周囲から「もっとちゃんとして」「いい加減にしなさい」と叱られがちです。しかし本書を活かして、時間感覚のズレや作業メモリの弱さなど、自分の弱点をリストアップしてみると、対策を立てやすくなる。たとえば「毎朝の身支度に何分かかるか」を正しく把握するだけでも、遅刻癖が劇的に改善することもあるのです。
認知行動療法で「できない思考」をほぐす
ADHDを持つ方の中には、「頑張っているのに同じ失敗を繰り返す」「周囲に迷惑をかける」といった経験から、否定的な自己イメージが強まっている場合があります。「自分は何をやっても上手くいかない」「またミスするに決まっている」という思考パターンに支配されやすいのです。
こうした思考パターンを修正するのが、認知行動療法(CBT)の重要な役割。CBTでは、「自分がどんな考え方をしてしまいがちか」を客観的に観察し、「その考え方は本当に正しいのか?」と検証していきます。具体的には、以下のようなプロセスがあります:
- 自分の思考を記録:例えば「ミスをした → やっぱり自分は能なし」という思考が浮かんだら、その場で書き留める。
- その裏付けや反証を探す:「本当に能なしなのか? 過去に上手くやれた例はないか?」など、客観的に見る。
- よりバランスの取れた考え方に変換:「自分にも改善できる部分はある。ミスしたが一部はうまく対処できた」といった再解釈を試す。
こうした手続きを継続することで、自動的に浮かぶ「自分を否定する思考」に振り回されにくくなるのです。本書には、こうした思考記録や検証のプロセスを実践的に進めるフォーマットや宿題の仕方が紹介されており、専門家の支援下でも、自分自身で取り組んでもある程度活用できます。
時間管理と優先順位づけの具体的技法を習慣化する
成人ADHDの人がよく抱える悩みとしては、「やるべきことを把握していても、それを整理して行動に落とし込めない」というものがあります。そこで本書のプログラムは、きわめて具体的な行動習慣――時間割りの作り方やタスクリストの書き方、デッドラインの設定といったテクニック――を示してくれます。
ポイントは「習慣化」というところ。成人ADHDでは一度やり方を学んでも、飽きてしまったり面倒になって続かないというケースが多いものです。本書では、その継続をどうサポートするかに焦点を当てていて、以下のような工夫が推奨されます:
- 小さな成功体験を積み重ねる:最初はほんの少しの時間管理でもできたら自分を褒めたり、報酬を設定する。
- 外部リマインダーを使い倒す:スマホのアラームやカレンダー通知、ポストイットなど、とにかく忘れない仕組みを作る。
- 同じ時間帯に同じルーティンを行う:朝起きたらすぐ手帳を見てタスクリストを確認…というように、行動を紐づける。
これらはシンプルな方法に思えますが、ADHDの特性からすると「シンプルこそ効果的」であり、しかもルーティンの定着が非常に重要。常に工夫を重ねて習慣化を目指すというアプローチが、本書では繰り返し強調されています。
ハイパーフォーカスや創造性をポジティブに活かす工夫
ADHDの人は、集中力が散漫になりやすい一方で、「ハイパーフォーカス」と呼ばれる極端に集中が高まる状態を経験することもあると言われています。自分が興味を持った対象に対しては並外れた集中力を発揮し、長時間没頭することができるのです。
本書は、そうした特性を「欠点」ではなく、「強み」として捉える方法をサポートする点が特徴的です。ハイパーフォーカスは周囲の時間感覚を忘れてしまうリスクも伴うので、そのエネルギーを仕事や学習にどう結びつけるかが課題です。例えば:
- 集中が高まる時間帯を活用:朝早い時間や夜など、自分がより没頭しやすいタイミングに重要タスクを配置する。
- 環境を整える:他の刺激を可能な限り排除し、没頭してよい環境をあえて作る。
- タイマーを用いて区切りを作る:ハイパーフォーカスに入って何時間も経過してしまうのを防ぐため、休憩を強制的に挟む仕組みを持つ。
これにより、ADHDの人が持つ天性の「探究心」や「新しいものに熱中する力」を、実際に成果を生み出す形で活かすことができます。まさに本書が目指しているのは、ADHDを単に「直す」ことではなく、その特徴をどう社会や個人の成長に繋げるかという発想です。
認知と行動の両面から「成長マインドセット」を育む
「ADHDを抱えているから自分はダメだ」「どんなにやっても結果は同じ」という諦めの感情が強くなると、成長のチャンスを自ら閉ざしてしまいがち。ところが本書で紹介されるCBTプログラムは、ADHDの人たちが日々の小さな成功体験を重ねることで、「少しずつできるようになっている」という実感を持てるよう、ステップバイステップで組まれています。
いわゆる「成長マインドセット」と呼ばれる、「スキルは努力次第で向上しうる」という考え方を、この療法のプロセスの中で体得するわけです。具体的には:
- 失敗した時の思考記録:そこで得た学びを確認し、次の試行につなげる。
- 少しでも前回よりマシなら成果として認める:たとえば、遅刻の回数が週に5回から3回になったら自分を認める。
- スキル向上に目を向け、絶対的な完璧さを求めない:100%できなくても、70%できれば大きな成長と捉える。
このような考え方を普段から実践することで、「ADHDの特性は絶対的な欠点ではなく、工夫次第で改善できる」という確信が生まれてきます。薬によって症状をコントロールするだけでは得られない、深い自尊感や自己効力感を育むことができるのが、認知行動療法の大きな魅力です。
所感
ADHDと聞くと、多くの人は「落ち着きがない」「不注意が目立つ」「仕事ができない」といったネガティブなイメージをまず浮かべてしまいがちです。特に大人のADHDは周囲からの理解も得にくく、本人も「もう少しちゃんとできないものか」と自分を責めてしまうケースが多いでしょう。しかし、この本を読むと、ADHDを「治す」だけでなく、「使いこなす」という視点を得られる点がとても印象的でした。
著者のソラント氏は、数多くの患者と向き合いながら、実行機能障害がどのように日常を混乱させるか、そしてそこを丁寧に補うやり方(認知行動療法)をどのように実践すればよいかを具体的に提示しています。時間管理やタスクリスト、集中力をサポートするツールなど、すぐにでも取り入れられるノウハウが豊富にあるため、「どうしたらいいのかわからない」という人にとっては一種の羅針盤になるはず。
また、単なる表面的な行動療法ではなく、「なぜ自分はこう考えてしまうのか」「否定的な思考をどう客観視するのか」という内面へのアプローチもセットになっているため、精神的な負担を軽減したりモチベーションを高めたりする効果が期待できます。ADHDの特性を否定するのではなく、「ここは苦手だけど、そこを支える仕組みを作れば得意分野をもっと伸ばせる」というポジティブな方向に導いてくれる点が、このプログラムの最も素晴らしいところではないでしょうか。
まとめ
『成人ADHDの認知行動療法 実行機能障害の治療のために』は、単なる治療マニュアルにとどまらず、ADHDの特性を人生でどのように活かすかを示してくれる大変貴重な一冊です。大人のADHDはしばしば「仕事がうまくいかない」「周囲とトラブルが増える」などネガティブな側面ばかり強調されますが、実は同じ特性を活かして創造性や好奇心に溢れた力を発揮できることも事実。本書は、その実行機能障害に対してどう認知行動療法を使い、具体的な行動面の改善や思考パターンの書き換えを進めるかを細かくガイドしてくれます。
特に「活用法」として、以下のようなポイントが挙げられました:
- 自分の実行機能の弱みを把握し、タスクの組織化や時間管理の問題点を客観視する。
- 認知行動療法でネガティブな思考パターンを修正し、「自分は成長できる」視点を育む。
- 具体的な行動習慣を定着させる:タイマー活用、タスクリスト作成、スモールステップでの学習など。
- ハイパーフォーカスを上手く活かす仕掛け:没頭しやすい環境を整えつつ、タイマーなどで区切りをつくる。
- 失敗や無駄を許容しながら習慣化し、段階的にスキルアップを図る。
これらは実にシンプルなようでいて、実行するにはコツやサポートが欠かせません。だからこそ本書は臨床家だけでなく、本人や家族が読むことで、「ああ、こういうやり方があるのか」「こうすれば自分も少しずつ前に進めるんだ」と納得感を得られるのではないでしょうか。
もちろん、薬物療法だけでは不十分という声もある中で、こうした心理社会的アプローチが存在し、多くの臨床研究で有効と認められはじめているのは心強い事実です。ADHDを「欠点」と捉えるよりも、「特性」として認め、その上でどう社会に生かすかを考える方が本人の幸福や周囲の理解にも繋がるでしょう。本書はそのための具体的かつ実践的な道を示しており、ADHDに関わる人々にとっての貴重な指針となってくれそうです。

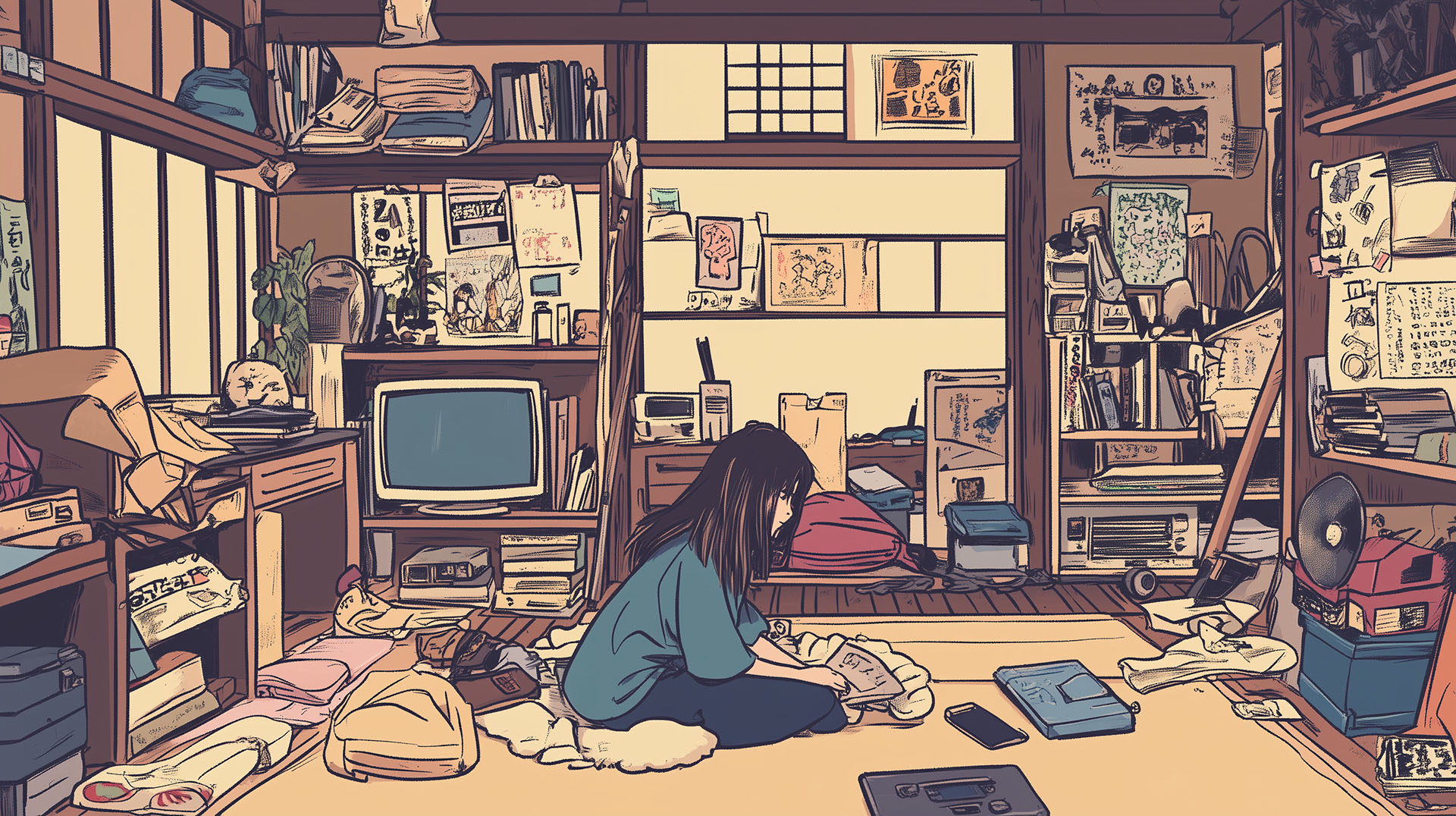


コメント