著者・出版社情報
著者:安藤広大
出版社:ダイヤモンド社
概要
プレーヤー(個人として成果を出す役割)からマネージャーに昇進したばかりの人は、多くの場合、「リーダーとしても自分が率先して結果を出し続けなければいけないのではないか」「部下に好かれる上司でありたい」といった思いを抱きがちです。けれども、組織を本当の意味で成果に導くためには、それらとはまったく違う視点やマインドが必要になる――本書『リーダーの仮面 ── 「いちプレーヤー」から「マネジャー」に頭を切り替える思考法』は、そうした「マネジャーへの頭の切り替え」の重要性を説いています。
著者の安藤広大氏は、マネジメントを科学的にアプローチする「識学」で知られる実務家。プレイヤーとして成功してきた人がリーダーになる際、意外なほどに陥りやすい落とし穴を指摘し、そこから抜け出すための具体的な指針を本書で提示しています。「リーダーの仮面」とは何か。なぜ嫌われる勇気が必要なのか。なぜ部下と深く打ち解けすぎないほうが成果につながるのか。その一つひとつが、本書で解説されている要諦です。
「どうすればリーダーとして、部下に明確な行動指針を示し、成果を上げさせる組織を作れるのか?」という問いに対して、本書は「感情ではなく合理」「ぬるい優しさではなく、適切な距離感」「成果を目指す厳しさが、本当の意味で部下を救う」といったメッセージを強く打ち出しています。大人になるほど「仲良く、気持ちよく」やりたいという思いが強まるかもしれませんが、それだけではチームは導けない。長期的な視点で見れば、厳しさをもって部下に向き合うほうがかえって組織を活性化し、部下自身の成長にも資するというのが著者の主張です。
活用法
リーダーの自分と個人の自分を分けて考える
プレイヤー時代の「自分らしさ」や「部下に好かれる」ことを重視していると、リーダーとしての役割を全うする際に心理的に苦しくなるのが常です。なぜなら、リーダーとして下すべき決断や伝えるべき指示は、ときに部下に嫌われるものだったり、厳しく見えるものだったりするかもしれないからです。
本書が強調する「リーダーの仮面」とは、まさにこのギャップを埋めるための考え方。自分の人格(好かれたい、仲良くしたい)と、リーダーとして組織を率いるために必要な態度は別物だと割り切る、というのです。たとえば部下に厳しいノルマを課すとき、「個人的には申し訳ない気持ち」を感じても、リーダーとしては目標達成のために言い切らなければならない。一時的に嫌われても仕方ない――それこそが「リーダーの仮面」をかぶるということ。
このとき、あえて自分とリーダー役を分離する意識を持つと楽になる、と著者は説きます。これは演じているわけではなく、役割を全うする一つの手段。相手の感情に同調しすぎると、組織の目標と妥協してしまいがち。だからこそ「リーダーという仮面」をかぶり、「自分が最終責任者として部下に厳しい決断を伝える役」として行動できるのです。
ルールや評価の基準を徹底し、感情に流されない組織を築く
多くの日本の職場は、表向きはルールを定めていても曖昧な運用をしていたり、場の空気や先輩後輩関係など「情」に左右される部分が大きかったりします。その結果、部下のやる気や成果が客観的に評価されず、どこか混乱した状態になることがあるでしょう。
本書は、明文化されたルールを厳密に遵守することを強く推奨しています。例えば、
- 遅刻にはどう対処するか
- ノルマ未達はどのように評価されるのか
- ミーティングの出欠や報連相の基準をどうするか
など。これらを「感情的に見逃す」「仲が良い部下には甘くする」などをやっていると、組織は曖昧になり、かえってトラブルの元になるというわけですね。
リーダーがやるべきなのは、ルールを決め、徹底させること。最初は「厳しすぎる」「融通がきかない」と反発があるかもしれませんが、長い目で見ると、チームの雰囲気はむしろ良くなる。なぜなら、部下たちが「そのほうがフェアだ」と感じられるからです。
また、評価の基準をプロセスではなく「結果」で判断するのも肝だと著者は言います。いくら頑張っているように見えても成果が出ないなら評価は低いし、成果を出しているなら過程がどうであれ高く評価するという姿勢。情や過程に流されず「結果に責任を持たせる」のがリーダーの仕事だと、本書は繰り返し説いています。
部下との距離感:仲間のように接しすぎない
プレイヤー時代は一緒に飲みに行ったり、雑談を楽しんだりして仲良くしていた相手が、いきなり部下になることもあるかもしれません。そんなとき、「以前と同じように親密な関係でいたい」と思うあまり、上司としての指示やマネジメントが曖昧になってしまうケースがよくある。
本書では、それは危険だと警鐘を鳴らしています。なぜなら、マネージャーは部下を評価し、指示を出し、成果に責任を持つ立場だからです。そこに過度な「親しさ」が入り込むと、公正な評価や厳しい決断ができなくなる恐れが高い。また、部下のほうも「友達のような上司から指示されるのはやりにくい」と感じる場合が多いのが現実だと本書は言います。
大切なのは、「適度な距離感」を保ったコミュニケーション。上司と部下という関係を明確にしつつ、必要なときに必要な情報を与え、指示を下し、結果を確認する。過度に干渉したり、感情を共有しすぎるのではなく、一歩引いた立場から部下を成長させるよう誘導していく。著者は、そうした態度こそが組織の効率と人材の育成の両面で好結果を生むと強調しています。
結果にフォーカスし、部下が自走する仕掛けを作る
プレイヤー時代は「自分が誰よりも頑張って成果を出す」ことが評価の源泉でした。ところがマネジャーになると、自分がいくら頑張っても部下が成果を出さなければ、チーム全体としての結果は上がらない。ここが思考の大きな転換点です。本書は、マネジャーは“部下に成果を出させる”のが仕事であって、「自分が先頭に立って頑張る」のは逆効果になることもあると解説しています。
では、どうやって部下に自発的な行動を起こさせるか。ここでのキーワードは「結果への責任」を部下に明確に持たせることです。
- プロセスには口を出しすぎない
- 結果が出なければ評価は下がるというルールを共有する
- 困ったときだけ上司に相談する体制を築き、上司は最終責任を持つ
このようにすれば、部下は「上司の指示どおりに動くのではなく、自分の頭で考え、結果を出さなければならない」と腹をくくる。プレイヤー時代のように上司が細部まで指示を出すと、部下は受け身のまま「上司のせいにする」傾向が強まります。
いっぽう上司が「結果重視」を明確に打ち出すと、部下は不満やストレスを感じるかもしれませんが、それが適度な緊張感となって自走を促すと本書は説明します。また、自走する分だけ部下は成長し、組織全体のパフォーマンスも引き上がる――ここが「リーダーの仮面」による厳しさが、実は部下を救うという本書の主張の核心です。
嫌われる覚悟で、長期的に「部下の成長」に貢献する
「部下と仲良くやりたい」「嫌われたくない」という気持ちは、多くの新任マネージャーが抱える感情でしょう。ところが本書は、「厳しいことを言えば部下に嫌われるかもしれない。だがそれが本当の優しさだ」と説きます。
たとえば部下が苦手な業務に挑戦して失敗しそうなとき、「本人が嫌がるなら、まぁいいか」と甘やかすのは短期的には和やかかもしれませんが、長期的には部下の成長機会を奪うことになります。逆に、「これはお前にとって必要だから、失敗しても構わんがやれ」と厳しく指示することが、部下のスキル向上を促し、将来的には本人のメリットにもなるわけです。
実際、子供のころ厳しい教師に反発していたが、後から「当時の厳しさのおかげで成長できた」と感謝するようなエピソードはよく耳にします。本書のメッセージも同様で、一時的な嫌われ役を引き受けるというのがリーダーの仕事。これには勇気が要りますが、長い目で見れば、部下はその厳しさをバネにしてぐんぐん成長し、リーダーとしても組織の成果を出しやすくなるのだと説かれています。
所感
日本ではこれまで、「部下から信頼され、慕われる上司」が理想像として語られてきました。しかし、本書を読むと、それが必ずしも組織の成果や部下の成長に繋がらないばかりか、むしろ甘やかしになってしまう可能性があると気づかされます。「リーダーの仮面をかぶる」とは、ある種の割り切りであり、決して人間味を捨てることではなく、「リーダーという役割を淡々と全うする」ことなのだなと感じます。
この考え方には賛否両論があるかもしれません。部下との強固な信頼関係を築くためには、ある程度の親和的コミュニケーションも必要だろうし、あまりにドライに成果のみを求めると心理的安全性を損なうリスクもあるでしょう。しかし、本書で述べられるのは「結果のためには、一定の厳しさやルール、評価基準の明確化が欠かせない」という点。そしてそこが、組織を強くし、部下を本質的に伸ばす上で重要なのは確かかもしれません。
個人的に印象深いのは、「上司が感情的にならず、部下と距離を取りながら合理的に接するほうが、部下はかえって安心して行動できる」という指摘。私たちは、しばしば「皆仲良くやるほうが良い」と思い込みがちですが、曖昧な上下関係やルール不在の職場では、かえって不公平感や生産性の低下が起こりやすい。冷たいようでいて、確固たるルールと明確な評価基準があるほうが、メンバーは実力や努力をちゃんと認めてもらえる期待が持てる、というわけですね。
まとめ
『リーダーの仮面 ── 「いちプレーヤー」から「マネジャー」に頭を切り替える思考法』は、プレイヤーとして優秀な結果を出してきた人が、いざマネージャーになったときに陥りがちなミスを、行動心理学的観点から詳細に分析し、その解決策を提示する書籍です。多くの新任リーダーが「成果を出すには、部下と仲良くし、皆が気持ちよく働ける雰囲気を作ればいいのでは?」と考えがちなのを、「それは必ずしも正解ではない」と切り捨てるところが非常に特徴的。
むしろ本書は、「リーダーは好き嫌いではなく、ルールと結果を軸に組織を動かすべきだ」「部下との馴れ合いを避け、厳しいルールを徹底するほうが長期的には部下を幸せにする」と説きます。一見冷淡にも聞こえるかもしれませんが、現実のビジネス現場では、この合理的アプローチのほうが成果を出しやすく、組織に役立つというのです。
特に「初めて部下を持つ」「管理職デビュー」という方には必読と言えます。自分がどう部下を評価し、どう指示を出し、どう責任を共有するのか――その新しい役割に「どう振る舞えばいいのか」で悩む方は多いはず。本書はまさにそうした疑問への答えを、ロジカルかつ具体的に示してくれるのが魅力です。
気になるのは「厳しすぎる管理」「上下関係を重視しすぎるスタイル」が日本的な協調文化とどう共存できるかという点ですが、本書は「厳しさ」と「合理性」を履き違えないことの大切さ、そして「部下と無闇に仲良くなりすぎない」だけで、相互理解を否定しているわけではないと解釈できます。「リーダーの仮面」というコンセプトは、人間関係を破壊するものではなく、組織のために必要な役割を演じる、という意味でむしろ建設的なのです。
最終的に本書が伝えたいのは、リーダーとして嫌われることを恐れず、しかし冷淡ではなく、明確なルールと評価を設定して部下を導くこと。その結果、部下は自分自身の成果に責任を持ち、組織は最大限に力を発揮できる――だからこそ「リーダーの仮面」をかぶる価値があるのだと。本書の内容を一度でもしっかり読み込めば、プレイヤーからマネージャーへの転換期がグッと楽になるでしょう。根性や精神論とは異なる切り口で語られる、合理的かつ少し厳しいマネジメントのススメは、多くのリーダーにとって新鮮な発見となるはずです。

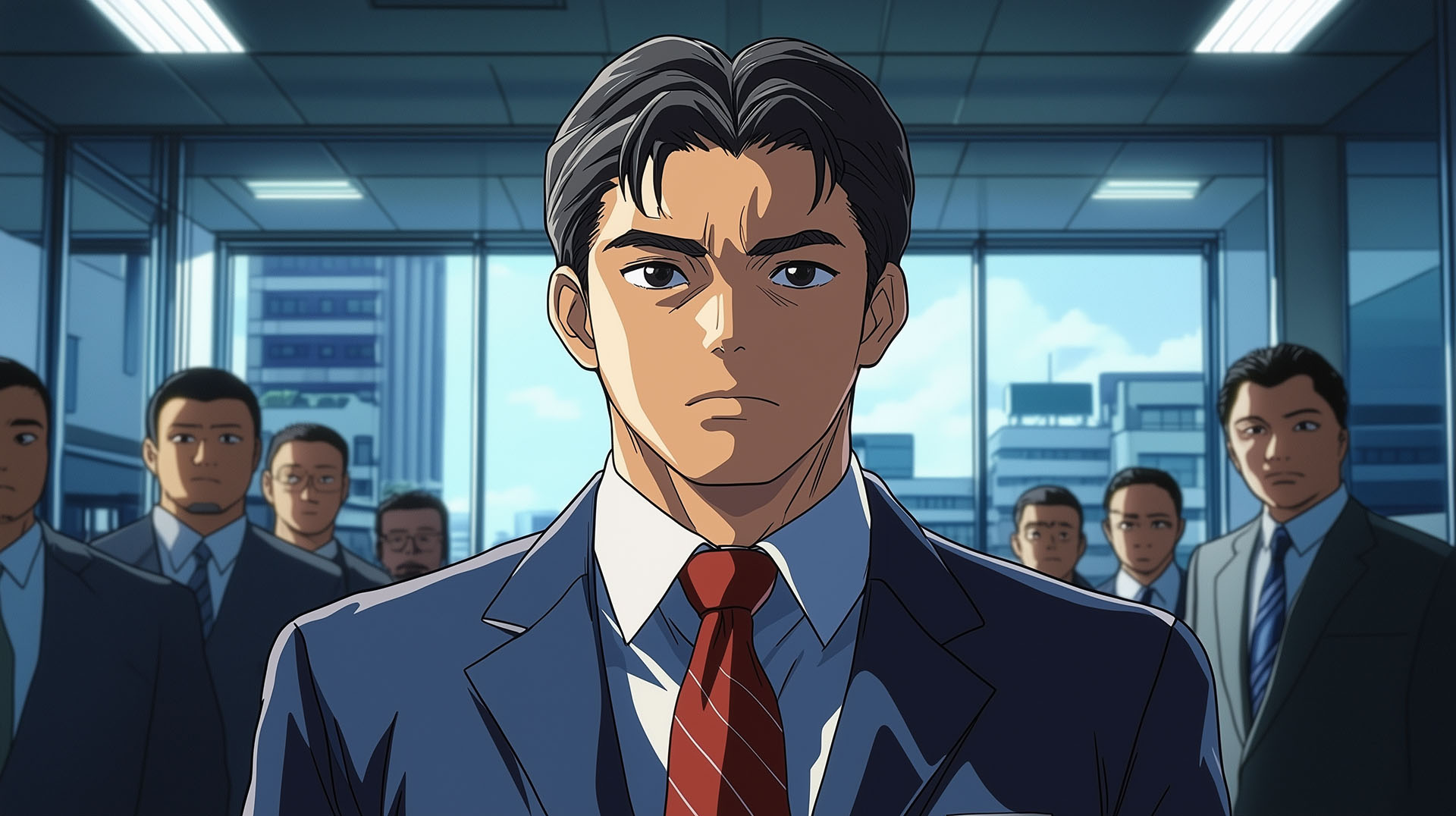


コメント