著者・出版社情報
著者:安藤広大
出版社:ダイヤモンド社
発行年:2020年
概要
「数値化の鬼」は、株式会社識学の代表取締役社長である安藤広大氏が提唱する、ビジネスパーソンが成果を最大化するための思考法を解説した一冊です。
本書のタイトルにもある「数値化」とは単なる数字の活用術ではなく、あらゆる目標や行動、成果を具体的な数値で表現し、客観的に分析・評価するための思考法です。組織で高く評価される人材になるための鍵は、曖昧な表現や感覚に頼らず、すべてを数値という「動かぬ事実」として捉える習慣を持つことだと安藤氏は主張します。
仕事において「頑張る」「改善する」「できるだけ早く」といった曖昧な表現ではなく、「訪問件数を10件増やす」「処理時間を15%短縮する」「14時までに提出する」という具体的な数値で表現することで、自分の行動の方向性が明確になり、目標達成への道筋が見えてきます。
本書では、「仕事ができる人」を「評価者から評価される人」と定義し、その評価を得るための5つのステップを詳細に解説しています。「行動量を増やす」「確率のワナに気をつける」「変数を見つける」「真の変数に絞る」「長い期間から逆算する」という段階的なアプローチを通じて、読者は自身の仕事の効率と成果を劇的に向上させることができます。
安藤氏自身が創業から4年あまりで上場を果たした経験や、多くの企業の業績向上に貢献してきた実績に基づいた、極めて実践的な内容となっています。
活用法
本書の内容を実際のビジネスシーンで活用するための具体的な方法をいくつかご紹介します。これらの活用法は、あなたの仕事の質を向上させ、成果を最大化するための指針となるでしょう。
すべての目標を数値化する習慣をつける
まず最も基本的なステップとして、日々の業務における目標をすべて数値化することから始めましょう。「今週はしっかり営業する」ではなく「今週は新規顧客20社に電話し、5件のアポイントを獲得する」というように、具体的な数字を設定します。
特に効果的なのは朝の時間を使って、その日の目標を数値化することです。例えば以下のような形で設定してみましょう:
– メール返信:午前中に30件完了させる
– 企画書作成:2時間以内に完成させる
– 顧客訪問:3社×各30分の訪問を行う
– タスク消化:To Doリストの項目を15件解消する
このように具体的な数値目標を立てることで、一日の終わりに「頑張った」という曖昧な達成感ではなく、「設定した15項目中12項目を達成できた」という客観的な評価が可能になります。
PDCAサイクルに数値を組み込む
よく知られたPDCA(Plan-Do-Check-Action)サイクルに数値を組み込むことで、そのサイクルは格段に効果的になります。
P(計画):目標を必ず数値で設定します。「売上を増やす」ではなく「第3四半期の売上を前年比15%増加させる」というように。
D(実行):実行段階でも、行動量を数値で管理します。「営業活動を増やす」ではなく「1日あたりの顧客接触数を現在の5件から8件に増やす」というように具体的に。毎日の行動量をエクセルやアプリで記録していくと良いでしょう。
C(評価):結果を数値で評価します。「まあまあうまくいった」ではなく「目標15%増に対して実績は12%増。3%の未達」というように、差異を明確に。
A(改善):次に向けた改善策も数値で設定します。「もっと頑張る」ではなく「顧客一人あたりの提案商品数を現状の2つから3つに増やす」というように。
このサイクルを例えば週次で回していくことで、行動と結果の因果関係が明確になり、効率的な業務改善が可能になります。特に、Cの評価段階で「なぜ目標未達だったのか」を数値で分析することが重要です。
KPI(重要業績評価指標)の効果的な設定方法
大きな目標(KGI)を達成するための中間指標であるKPIの設定も、数値化思考の重要な応用例です。
効果的なKPI設定のポイントは以下の通りです:
①数値化の徹底:KPIは必ず数値で表現します。「顧客満足度を高める」ではなく「顧客満足度調査で4.5以上(5点満点)を達成する」というように。
②最終目標との連動:KPIは最終目標(KGI)達成に直接貢献するものでなければなりません。例えば、最終目標が「売上300万円」なら、「見積書提出10件/週」というKPIは適切かもしれませんが、「名刺交換50件/週」は直接的な貢献度が低いかもしれません。
③行動への具体性:KPIは「何をすべきか」が明確になるレベルまで分解されている必要があります。「英語力向上」というKPIは曖昧すぎますが、「TOEIC対策問題集を1日30問解く」なら具体的な行動に落とし込めます。
④適切な数と優先順位:KPIは5つ以内に絞り込むことが理想的です。多すぎると焦点がぼやけ、何にリソースを集中させるべきか不明確になります。
例えば、営業部門のKPI設定例:
– 新規アポイント獲得数:週20件
– 提案書提出数:週10件
– 成約件数:月8件
– 既存顧客フォロー面談:月顧客ごとに1回以上
KPIを設定する際は、「これを達成すれば確実に最終目標に近づく」という確信が持てるものを選定しましょう。
「行動量」と「確率」のバランスを意識する
安藤氏が強調する重要なポイントの一つが、「行動量」と「確率」のバランスです。短期的な成功率(確率)にとらわれて行動量を減らすことは、長期的な成果を制限してしまう危険性があります。
例えば、営業活動において契約率80%を誇る営業マンA(10件訪問中8件成約)と、契約率50%の営業マンB(50件訪問中25件成約)がいた場合、実際の成果はBの方が圧倒的に大きいことになります。
この「確率のワナ」に陥らないための実践的アプローチとして:
①行動量の数値目標を設定する:「1日に電話30件、訪問5件」など、行動量そのものに具体的な目標を設定します。
②行動量と成功率を別々に記録する:例えば、「提案数」と「成約率」を別々の指標として記録・管理し、両方を意識します。
③行動量が減少したら警報を鳴らす:行動量が一定水準を下回った場合に警告する仕組みを作り、無意識の行動量減少を防ぎます。
④行動量の質を高める工夫をする:単に数をこなすだけでなく、「より効果的な行動」を模索します。ただし、これは十分な量をこなした後の話です。
特に業績が厳しい時ほど「もっと効率的に」と考えがちですが、まずは「行動量が落ちていないか」を確認することが重要です。安藤氏は「行動量が一定以上あれば、結果はついてくる」と主張しています。
「変数」と「定数」を見極める
効率的に成果を上げるために重要なのが、「変数」と「定数」の見極めです。
変数:自分の行動によって変えることができ、成果に影響を与える要素
定数:自分では変えられない、または変えても成果に影響しない要素
例えば、営業活動において:
変数の例:
– 訪問件数
– 提案内容の質
– 顧客への連絡頻度
– プレゼン資料の出来
定数の例:
– 競合他社の動向
– 景気状況
– 過去の失敗
– 顧客の予算制約
成果を上げるためには、「定数」にエネルギーを費やすのではなく、「変数」に集中する必要があります。特に重要なのが、ありとあらゆる変数の中から「真の変数」(最も成果に影響を与える要素)を特定することです。
変数を見つけるための具体的な方法:
①業務を細分化する:例えば営業活動を「リスト作成→アポ取り→訪問→提案→クロージング→フォロー」のように分解します。
②それぞれの段階で試行錯誤する:各段階で異なるアプローチを試し、どの変更が最も結果に影響するかを観察します。
③結果を数値で記録・分析する:「アポ取りの方法A」と「アポ取りの方法B」では、どちらがアポイント獲得率が高いかを数値で比較します。
④真の変数に集中する:最も成果に影響を与えると特定された1〜3つの変数に、リソースを集中させます。
このアプローチにより、「頑張った割に結果が出ない」というジレンマから脱却し、効率的に成果を上げることができるようになります。
バックオフィス部門での数値化
営業や企画部門と比較して、人事、総務、経理などのバックオフィス部門では数値化が難しいと感じられがちです。しかし、これらの部門でも数値化は可能であり、むしろ数値化により貢献度を可視化できるメリットがあります。
バックオフィス部門での数値化の例:
人事部門:
– 採用決定までの平均日数:45日以内
– 内定承諾率:80%以上
– 社員一人あたりの研修時間:四半期で10時間以上
– 離職率:年間5%以下
経理部門:
– 月次決算報告完了日:翌月第5営業日以内
– 請求書発行の正確性:エラー率0.5%未下
– 経費精算の処理時間:申請から支払いまで3営業日以内
総務部門:
– 備品発注リードタイム:平均2日以内
– 会議室予約システムの稼働率:90%以上
– コピー用紙使用量:前年比20%削減
– 社内イベント参加率:70%以上
これらの指標を設定・測定することで、「見えにくい貢献」を可視化し、客観的な評価基準を持つことができます。また、業務改善の効果も測定可能になります。
「長期的視点」から逆算する習慣をつける
目先の数字だけでなく、「5年後、10年後の自分(あるいは組織)はどうなっていたいか」という長期的視点から現在の行動を導き出す「逆算思考」も重要です。
具体的な実践方法:
①長期目標を明確に数値化する:「5年後に年収1,500万円」「10年後に部長職に就く」など。
②中間地点のマイルストーンを設定する:「2年後に主任」「3年後に課長」など、段階的な目標を設定。
③各マイルストーンで必要なスキルや実績を洗い出す:「課長になるためには●●という実績が必要」など。
④それを達成するための現在の行動目標を設定する:「今年中に●●の資格を取得する」「四半期ごとに●●%の売上増を達成する」など。
長期的視点から現在の行動を導くこの方法により、目の前の数字に一喜一憂することなく、一貫した方向性を持って行動することができます。また、短期的には非効率に見える行動(例:研修や資格取得など)に投資する根拠も明確になります。
「ニセモノの数字」と「本物の数字」を見分ける
数値化を推進する際に注意すべき点として、「ニセモノの数字」の存在があります。これは、一見数値化されているように見えて、実は測定基準が曖昧なものを指します。
ニセモノの数字の例:
– 「コミュニケーション能力を10%向上させる」
– 「仕事の効率を2倍にする」
– 「プレゼン力を高める」
これらは数字や「向上」という言葉を使っていても、何をどう測るのかが不明確です。
対して「本物の数字」の例:
– 「会議での発言回数を1回から3回に増やす」
– 「レポート作成時間を現状の4時間から2時間に短縮する」
– 「プレゼン評価アンケートで4.0以上(5点満点)を獲得する」
真の数値化は、誰がいつ測定しても同じ結果が得られる客観性を持っています。数値化を実践する際は、この「測定可能性」を常に意識することが重要です。
日常生活への応用
数値化思考はビジネスだけでなく、プライベートや自己啓発にも応用可能です。
健康管理の例:
– 「健康になる」→「毎日8,000歩歩く」「週3回30分の運動をする」
– 「減量する」→「3ヶ月で5kg減量する」「1日の摂取カロリーを1,800kcalに抑える」
趣味・スキルアップの例:
– 「ピアノが上手くなる」→「1日30分の練習を毎日続ける」
– 「読書習慣をつける」→「1日30ページ、月に5冊の本を読む」
時間管理の例:
– 「SNSの時間を減らす」→「1日のSNS使用時間を30分以内に制限する」
– 「早起きする」→「平日は6時に起床する」
このように日常生活のあらゆる面で数値化を実践することで、漠然とした目標が具体的な行動計画に変わり、習慣化や目標達成が格段に容易になります。
チームへの導入方法
数値化思考をチーム全体に広めるための具体的なステップも重要です。
①小さな成功体験から始める:まず一部のプロジェクトや業務で数値化を試み、その効果を示します。
②「行動量」の数値化から着手する:最も理解しやすい「行動量」の測定から始め、徐々に範囲を広げていきます。
③定期的な振り返りの場を設ける:週次や月次で数値目標の達成度を振り返る時間を設け、PDCAサイクルを確立します。
④数値化の効果を共有する:「数値化導入前と後でこれだけ結果が変わった」という事例を共有し、納得感を醸成します。
⑤評価制度にも数値基準を導入する:曖昧な評価ではなく、事前に合意した数値目標の達成度に基づく評価を行います。
数値化思考の導入は、チームに「共通言語」をもたらし、属人的な判断や感情に左右されないコミュニケーションを可能にします。また、期待値のすり合わせが明確になり、「頑張ったのに評価されない」というフラストレーションも減少します。
所感
安藤氏の「数値化の鬼」を読み進めるうちに、私は自分自身の仕事への取り組み方を振り返らざるを得ませんでした。曖昧な「頑張る」という言葉に安住し、具体的な行動目標を設定せずに日々を過ごしてきた部分が少なからずあったことに気づいたのです。
特に印象的だったのは、「確率のワナ」についての指摘です。成功率を高く保とうとするあまり、チャレンジングな案件を避けたり、行動量を減らしたりする心理は、自分にも思い当たるところがありました。数値で考えることで、「10件中8件成功(80%)」よりも「50件中25件成功(50%)」の方が絶対数として価値が高いという当たり前の事実が、改めて鮮明に浮かび上がってきます。
また、「変数」と「定数」の考え方も非常に実践的です。自分ではコントロールできない外部環境に心を砕くのではなく、自分の行動で変えられる要素に集中するという原則は、仕事における無駄な不安やストレスを減らす効果があります。
一方で、この本を読んで感じた疑問点もあります。数値化が難しい創造性や人間関係の質といった側面をどう評価するのか。数値化がもたらす心理的プレッシャーとどう向き合うのか。また、短期的な数値目標の追求が長期的な価値を損なう可能性はないのか。
しかし、安藤氏も終章で述べているように、「数字がすべてではない」という境地に達するためには、まず数値化を徹底的に実践し、客観的な成果を出すことが前提となります。感情や直感の価値を語るのは、数値という客観的な現実を完全に掌握した上でこそ意味があるのでしょう。
この本を通じて、数値化は単なるテクニックではなく、仕事と向き合う姿勢そのものを変える思考法であることを学びました。すべての事象を客観的に捉え、効率的に成果を上げるための羅針盤として、今後の仕事に積極的に取り入れていきたいと思います。
まとめ
「数値化の鬼」は、曖昧さを排除し、具体的な数値に基づいて仕事に取り組むことの重要性を説いた一冊です。安藤広大氏が提唱する数値化思考は、単なる数字の活用術ではなく、客観的な事実に基づいて行動し、評価される成果を出すための体系的なアプローチです。
本書の核心は「いったん数字で考える」習慣の徹底にあります。目標設定、行動計画、進捗管理、結果評価のすべての段階で数値を用いることで、認識のズレを防ぎ、無駄なコミュニケーションコストを削減し、本質的な業務に集中できるようになります。
5つの成長ステップ(行動量の増加→確率のワナへの警戒→変数の特定→真の変数への集中→長期的視点からの逆算)を実践することで、「仕事ができる人=評価者から評価される人」への道筋が明確になります。
数値化思考は営業やマーケティングといった成果が見えやすい部門だけでなく、バックオフィス部門や日常生活にも応用可能です。すべての活動を測定可能な形で捉え、客観的に評価・改善していくことで、継続的な成長を実現できます。
本書は、安藤氏自身の経験と識学理論に基づいた極めて実践的な内容となっています。数値化を徹底することで、感情や曖昧さに惑わされず、確実に成果を出す「仕事ができる人」へと成長する道筋が示されているのです。
最終的に、数値化という客観的な羅針盤を手にすることで、私たちは仕事における無駄な迷いを排除し、効率的に目標を達成する力を手に入れることができるでしょう。そして、その先には数値だけでは測れない「やりがい」や「達成感」が自然とついてくるのです。

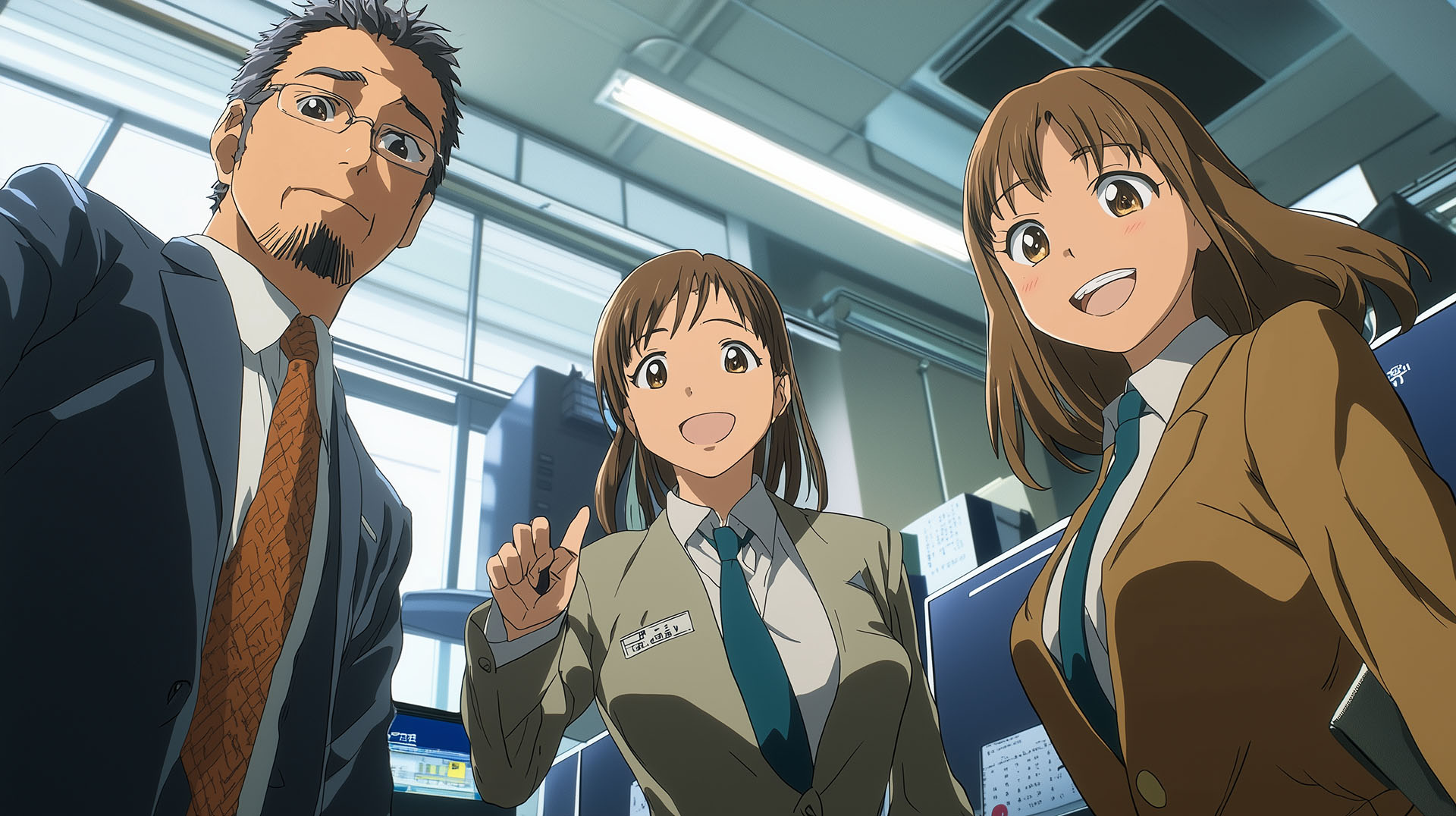


コメント